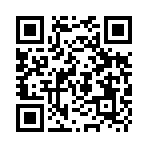2012年01月23日
モニターツアー意見交換会
こんにちは。
取材スタッフのケンです。
今回のモニターツアーの最後に、賎機(しずはた)都市山村交流センター安倍ごころにて、
しずおかの恵み体感協議会が制作した誘致用DVDによる、山の体験の概要説明と意見交換会が行われました。


ひととおり行程を終えた先生方からは、
「歴史的にも非常に勉強になる内容だった。食べ物がおいしいのも印象的。是非今後の参考にしたい。」
旅行会社のから方は、
「こういった教育体験旅行は子どもたちだけでなく、大人にも楽しめる内容であり、
是非大人向けにもツアーを組みたい」
という意見がありました。
一緒に静岡を盛り上げたいですね。
静岡市内のまだあまり知られていない体験、名所、伝統芸能…
個人的にもとても楽しい経験をさせてもらいました。
子どもたちがこれらの体験で、何に気が付き、どんな成長を見せるか、
来年度以降の教育体験旅行が今からとても楽しみです。
海の体験だけではない、山や川の体験もある静岡市!
今回のモニターツアで、静岡市の良さを再確認することができました。
取材スタッフのケンです。

今回のモニターツアーの最後に、賎機(しずはた)都市山村交流センター安倍ごころにて、
しずおかの恵み体感協議会が制作した誘致用DVDによる、山の体験の概要説明と意見交換会が行われました。


ひととおり行程を終えた先生方からは、
「歴史的にも非常に勉強になる内容だった。食べ物がおいしいのも印象的。是非今後の参考にしたい。」
旅行会社のから方は、
「こういった教育体験旅行は子どもたちだけでなく、大人にも楽しめる内容であり、
是非大人向けにもツアーを組みたい」
という意見がありました。
一緒に静岡を盛り上げたいですね。

静岡市内のまだあまり知られていない体験、名所、伝統芸能…
個人的にもとても楽しい経験をさせてもらいました。
子どもたちがこれらの体験で、何に気が付き、どんな成長を見せるか、
来年度以降の教育体験旅行が今からとても楽しみです。

海の体験だけではない、山や川の体験もある静岡市!
今回のモニターツアで、静岡市の良さを再確認することができました。

2012年01月22日
2日目、有東木集落の見学
こんにちは。
取材スタッフのケンです。
静岡教育体験旅行モニターツアー2日目。
梅ヶ島の隣町、有東木(うとうぎ)集落での山葵(わさび)田を見学しました
有東木は山葵栽培発祥の地です。(詳しくは前回の記事で)
2011年10月はじめにも訪れた場所ですが、
やっぱりここから見る景色は素晴らしいです。

参加した先生方と一緒に集落を見学したり、山葵の説明を受けたりしました。

山葵の葉っぱを食べさせてもらいました。
葉っぱだったのですが、ほのかにわさびの風味がありました。
私たちも滅多に見ることのない山葵ですが、
実際に農家の方と話して食べさせてもらうことによって、子どもたちにも
『ほんもの』
の体験をしてもらいたい、と感じた有東木でした。
次回は引き続き有東木の様子をレポートします。
取材スタッフのケンです。

静岡教育体験旅行モニターツアー2日目。

梅ヶ島の隣町、有東木(うとうぎ)集落での山葵(わさび)田を見学しました

有東木は山葵栽培発祥の地です。(詳しくは前回の記事で)
2011年10月はじめにも訪れた場所ですが、
やっぱりここから見る景色は素晴らしいです。


参加した先生方と一緒に集落を見学したり、山葵の説明を受けたりしました。

山葵の葉っぱを食べさせてもらいました。
葉っぱだったのですが、ほのかにわさびの風味がありました。

私たちも滅多に見ることのない山葵ですが、
実際に農家の方と話して食べさせてもらうことによって、子どもたちにも
『ほんもの』
の体験をしてもらいたい、と感じた有東木でした。

次回は引き続き有東木の様子をレポートします。
2012年01月21日
梅ヶ島で交流会★
こんにちは!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!

梅ヶ島の方々との交流会です!
梅ヶ島の方々が、横浜の子どもたちを受け入れた時の感想を発表しました。
「子どもを受け入れるのは初めてだったから緊張したよ」
「梅ヶ島で何に満足してくれるか考えた」など。
そして、梅ヶ島の方々は、子どもたちを、自分の本当の子どものように
扱うことを心がけていたようです
また有東木(うとうぎ)の方は、子どもたちと地域を散策したり話をしたりするのに、
「時間が少なくて説明し切れないところもあった」と言っていました。

次に、しずおかの恵み体感協議会の方が、横浜の子どもの体験旅行の様子を、
プロジェクターを使って、写真を見せながら行程毎に説明しました。
参加された先生方に好評で、個人的にも同行した時の思い出が蘇ってきました

また、協議会の方の話を聞いて、静岡市が一丸となって子どもたちの受入を盛り上げていこう!
という熱い意志を感じました。

教育体験旅行は、子どもたちの安全面や費用、先生方の負担が特に重要視されます。
それでも、体験した子どもたちの成長ぶりには驚くものがあり、
体験する価値は十分にあると思います!
教科毎の学習もそうですが、人間性も養われるからです。
協調性やおもいやり、コミュニケーション能力が身につくといった効果のほか
「普段目立たなかったのに、リーダーシップを発揮するようになる子もいる」
と、実際に小学校で体験旅行を経験した先生が言っていました。
是非、子どもたちに、静岡市でしかできないホンモノの体験を味わって成長してもらいたいですね
それにしても、梅ヶ島の夜空は星が近くてとてもきれいでした
市街地では見られない光景でした…

次回は静岡市モニターツアー2日目を紹介します!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!


梅ヶ島の方々との交流会です!

梅ヶ島の方々が、横浜の子どもたちを受け入れた時の感想を発表しました。
「子どもを受け入れるのは初めてだったから緊張したよ」
「梅ヶ島で何に満足してくれるか考えた」など。
そして、梅ヶ島の方々は、子どもたちを、自分の本当の子どものように
扱うことを心がけていたようです

また有東木(うとうぎ)の方は、子どもたちと地域を散策したり話をしたりするのに、
「時間が少なくて説明し切れないところもあった」と言っていました。
次に、しずおかの恵み体感協議会の方が、横浜の子どもの体験旅行の様子を、
プロジェクターを使って、写真を見せながら行程毎に説明しました。
参加された先生方に好評で、個人的にも同行した時の思い出が蘇ってきました


また、協議会の方の話を聞いて、静岡市が一丸となって子どもたちの受入を盛り上げていこう!

という熱い意志を感じました。
教育体験旅行は、子どもたちの安全面や費用、先生方の負担が特に重要視されます。
それでも、体験した子どもたちの成長ぶりには驚くものがあり、
体験する価値は十分にあると思います!

教科毎の学習もそうですが、人間性も養われるからです。
協調性やおもいやり、コミュニケーション能力が身につくといった効果のほか
「普段目立たなかったのに、リーダーシップを発揮するようになる子もいる」
と、実際に小学校で体験旅行を経験した先生が言っていました。
是非、子どもたちに、静岡市でしかできないホンモノの体験を味わって成長してもらいたいですね

それにしても、梅ヶ島の夜空は星が近くてとてもきれいでした

市街地では見られない光景でした…


次回は静岡市モニターツアー2日目を紹介します!

2012年01月20日
梅ヶ島 山の宿の夕ご飯☆
こんにちは!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!

山の宿くさぎ里(くさぎり)で温泉に浸かったら、いよいよ夕食です!

写真はヤマメのホイル焼きに、ヤマメのお刺身、お蕎麦、
有東木(うとうぎ)の山葵(わさび)漬けを挟んだかまぼこなどですが、
この後に、天ぷらに煮物、その場で焼く椎茸などが運ばれ、
梅ヶ島オールスターの食材を使ったお料理でした!
当然おいしかったです!

子どもたちも宿で食べる山のご飯は、普段食べないようなものばかりだと思うので、
味わいながら、料理や食材に疑問を持ち、
宿の方に「これは梅ヶ島で採れたものなんだよ」
「有東木は山葵栽培発祥の地なんだよ」などと教えてもらうことができます
このようなおいしい食の体験の中で、
有東木の山葵栽培や、ヤマメ、椎茸の話を通して、
地域の歴史や産業などが学べます
今回に限らず、地域の方から食べ物の説明を聞くことができる食の体験は、
その日に体験学習をしたことの復習やこれから体験することの予習ができるので、
とても大事だと思います。
ではまた次回です!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!


山の宿くさぎ里(くさぎり)で温泉に浸かったら、いよいよ夕食です!

写真はヤマメのホイル焼きに、ヤマメのお刺身、お蕎麦、
有東木(うとうぎ)の山葵(わさび)漬けを挟んだかまぼこなどですが、
この後に、天ぷらに煮物、その場で焼く椎茸などが運ばれ、
梅ヶ島オールスターの食材を使ったお料理でした!

当然おいしかったです!

子どもたちも宿で食べる山のご飯は、普段食べないようなものばかりだと思うので、
味わいながら、料理や食材に疑問を持ち、
宿の方に「これは梅ヶ島で採れたものなんだよ」
「有東木は山葵栽培発祥の地なんだよ」などと教えてもらうことができます

このようなおいしい食の体験の中で、
有東木の山葵栽培や、ヤマメ、椎茸の話を通して、
地域の歴史や産業などが学べます

今回に限らず、地域の方から食べ物の説明を聞くことができる食の体験は、
その日に体験学習をしたことの復習やこれから体験することの予習ができるので、
とても大事だと思います。
ではまた次回です!

2012年01月19日
梅ヶ島温泉の山の宿 くさぎ里(くさぎり)★
こんにちは!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!
大谷崩(おおやくずれ)を散策し、一同はいよいよ梅ヶ島温泉の宿へ
子どもたちは山での生活を体験します
梅ヶ島と言えば温泉地!と言えるくらい梅ヶ島温泉は有名です。
開湯は約1700年前と言われている、単純硫黄泉の温泉。
戦国時代には、武将たちの湯治場として親しまれてきたという長い歴史を持っています。
木造の素朴な旅館が多く、家庭的な雰囲気を持っています
旅館、民宿は12軒あります。


今回お世話になるのはくさぎ里(くさぎり)という宿。標高約870mの位置にあります。
中に入ると、玄関からは木の温もりが感じられ、おばあちゃんの家に帰ってきた気分になりました
ばぁちゃん元気かなー。。
そして玄関の横には囲炉裏が!

恥ずかしながら、私、初めて囲炉裏を体験しました。
ちょうどよい暖かさで心も落ち着きますねー
子どもたちも、囲炉裏を体験することはなかなかないと思います。
きっと子どもたちが体験旅行で訪れたら、夜、囲炉裏を囲みながら
宿の方と話をして、ふれあうんでしょうね
参加者みんな温泉に入り、疲れを癒しました♪
温泉に浸かった先生方は口々に「サイコー!」と言っていました
梅ヶ島温泉の湯はぬるぬるすべすべで、美肌効果が高いそうですよ♪
子どもたちにも、宿の温泉に入って、自宅のお風呂との違いを感じてほしいですね
では次回に続きます!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!

大谷崩(おおやくずれ)を散策し、一同はいよいよ梅ヶ島温泉の宿へ

子どもたちは山での生活を体験します

梅ヶ島と言えば温泉地!と言えるくらい梅ヶ島温泉は有名です。
開湯は約1700年前と言われている、単純硫黄泉の温泉。
戦国時代には、武将たちの湯治場として親しまれてきたという長い歴史を持っています。
木造の素朴な旅館が多く、家庭的な雰囲気を持っています

旅館、民宿は12軒あります。
今回お世話になるのはくさぎ里(くさぎり)という宿。標高約870mの位置にあります。
中に入ると、玄関からは木の温もりが感じられ、おばあちゃんの家に帰ってきた気分になりました

ばぁちゃん元気かなー。。
そして玄関の横には囲炉裏が!

恥ずかしながら、私、初めて囲炉裏を体験しました。
ちょうどよい暖かさで心も落ち着きますねー

子どもたちも、囲炉裏を体験することはなかなかないと思います。
きっと子どもたちが体験旅行で訪れたら、夜、囲炉裏を囲みながら
宿の方と話をして、ふれあうんでしょうね

参加者みんな温泉に入り、疲れを癒しました♪
温泉に浸かった先生方は口々に「サイコー!」と言っていました

梅ヶ島温泉の湯はぬるぬるすべすべで、美肌効果が高いそうですよ♪
子どもたちにも、宿の温泉に入って、自宅のお風呂との違いを感じてほしいですね

では次回に続きます!

2012年01月18日
インストラクターのお話から☆
こんにちは!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!
■大谷崩(おおやくずれ)の散策の続きです■

インストラクターが先生に
「この教育体験旅行において、子どもたちにまず好奇心をもってもらうことが大切。
そのためには体験学習中、できるだけ時間制限をなくし、押し付けるのではなく自由に学習させるようにしたい。」
と話していました。
子どもたちに自由に学ばせるためには、できるだけ時間の規制を少なくした、
余裕のあるプログラム、スケジュールを組むことが必要なんだなぁと思いました
ここ大谷崩を水源とする安倍川は、
水源から河口までが同一市内にあるという全国でも珍しい特徴を持っています。
横浜の子どもたちが静岡市に訪れた際もそうでしたが、静岡市の教育体験旅行は、
この安倍川を活かしたストーリー性のあるテーマのもとで、体験プログラムを提供することができるのです。
そのテーマによって、一連の流れに沿って静岡市の環境や歴史、産業などを学ぶことができ、
子どもたちの関心を引きやすくなっていることと思います。

最後に、見せてもらったミミズの化石です(笑)
わかりにくくてすみません…
それでは次回に続きます!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!

■大谷崩(おおやくずれ)の散策の続きです■
インストラクターが先生に
「この教育体験旅行において、子どもたちにまず好奇心をもってもらうことが大切。
そのためには体験学習中、できるだけ時間制限をなくし、押し付けるのではなく自由に学習させるようにしたい。」
と話していました。
子どもたちに自由に学ばせるためには、できるだけ時間の規制を少なくした、
余裕のあるプログラム、スケジュールを組むことが必要なんだなぁと思いました

ここ大谷崩を水源とする安倍川は、
水源から河口までが同一市内にあるという全国でも珍しい特徴を持っています。
横浜の子どもたちが静岡市に訪れた際もそうでしたが、静岡市の教育体験旅行は、
この安倍川を活かしたストーリー性のあるテーマのもとで、体験プログラムを提供することができるのです。
そのテーマによって、一連の流れに沿って静岡市の環境や歴史、産業などを学ぶことができ、
子どもたちの関心を引きやすくなっていることと思います。
最後に、見せてもらったミミズの化石です(笑)
わかりにくくてすみません…

それでは次回に続きます!

2012年01月17日
梅ヶ島と大谷崩散策★
こんにちは!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです

静岡市モニターツアーは駿府匠宿(すんぷたくみしゅく)からいよいよ梅ヶ島へ
過去にこのブログでもお伝えしましたが、僕たち取材チームは、
横浜の子どもたちの体験旅行に同行した際にも梅ヶ島を訪れています
子どもたちと違って先生方は梅ヶ島でどんなことを考えるんだろう…

再登場の大谷崩
日本三大崩れのひとつ。宝永地震(1707年)の際にできたものと言われています。
安倍川の水源にもなっており、ここの石が流れて、三保の海岸を作ります。
その証拠の…

ありました!2ヵ月ぶりのハチマキ石!
これより小さくて丸い石が三保にたくさんあるわけです。

散策しながら、生えている木や植物、落ちている石について、
インストラクターが子どもたちにしてくれたように、丁寧に、わかりやすく説明してくれます。
ハチマキ石が梅ヶ島から安倍川を伝って三保に流れていく話ももちろんしてくれました。
このインストラクターにより、梅ヶ島や大谷崩の歴史、地質など環境について学ぶことができます。
インストラクターが「大谷崩の石の中には、まれに水晶が含まれているものもあるんだよ」と話すと、

水晶入りの石を探す先生たち!
横浜の子どもたちも同じようにしていました(笑)
大人も子どもも宝さがしが大好きです!
もちろん水晶は見つかりませんでしたが…
ではまた次回!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです


静岡市モニターツアーは駿府匠宿(すんぷたくみしゅく)からいよいよ梅ヶ島へ

過去にこのブログでもお伝えしましたが、僕たち取材チームは、
横浜の子どもたちの体験旅行に同行した際にも梅ヶ島を訪れています

子どもたちと違って先生方は梅ヶ島でどんなことを考えるんだろう…
再登場の大谷崩
日本三大崩れのひとつ。宝永地震(1707年)の際にできたものと言われています。
安倍川の水源にもなっており、ここの石が流れて、三保の海岸を作ります。
その証拠の…
ありました!2ヵ月ぶりのハチマキ石!

これより小さくて丸い石が三保にたくさんあるわけです。
散策しながら、生えている木や植物、落ちている石について、
インストラクターが子どもたちにしてくれたように、丁寧に、わかりやすく説明してくれます。
ハチマキ石が梅ヶ島から安倍川を伝って三保に流れていく話ももちろんしてくれました。
このインストラクターにより、梅ヶ島や大谷崩の歴史、地質など環境について学ぶことができます。
インストラクターが「大谷崩の石の中には、まれに水晶が含まれているものもあるんだよ」と話すと、
水晶入りの石を探す先生たち!

横浜の子どもたちも同じようにしていました(笑)
大人も子どもも宝さがしが大好きです!
もちろん水晶は見つかりませんでしたが…

ではまた次回!

2012年01月16日
駿府匠宿で職人体験!
こんにちは。
取材スタッフのケンです。
静岡市教育体験旅行モニターツアー1日目
駿府匠宿(すんぷたくみじゅく)の見学です。
この施設は、静岡の匠の技を身近で見学しながら、
自らも様々な体験ができる施設です。

静岡市には、3代将軍徳川家光のときに、
駿府城建て替えのため、腕利きの職人を全国から召集したという歴史があります。
その職人たちがそのまま静岡市に定住したため、
多彩な伝統工芸が静岡市でも体験できるというわけなのです。
例えば、ひな人形、駿河和染、駿河竹千筋細工、駿河寄木細工などです。

中でも先生の目を引いたのが、この寄木細工。
職人の手によって板が複雑に組み合わさり、非常に精密な模様を作り出す様子は、
現代においても機械ではできないものです。
「どういうふうに作っているんだろう?」
「こういうふうにできてるんだぁ!」
という気付きが子どもたちには重要だと、参加した先生が教えてくださいました。
さすが先生…目の付け所が違います。
次回は山の体験、大谷崩れをレポートします。
取材スタッフのケンです。

静岡市教育体験旅行モニターツアー1日目
駿府匠宿(すんぷたくみじゅく)の見学です。
この施設は、静岡の匠の技を身近で見学しながら、
自らも様々な体験ができる施設です。

静岡市には、3代将軍徳川家光のときに、
駿府城建て替えのため、腕利きの職人を全国から召集したという歴史があります。
その職人たちがそのまま静岡市に定住したため、
多彩な伝統工芸が静岡市でも体験できるというわけなのです。

例えば、ひな人形、駿河和染、駿河竹千筋細工、駿河寄木細工などです。

中でも先生の目を引いたのが、この寄木細工。
職人の手によって板が複雑に組み合わさり、非常に精密な模様を作り出す様子は、
現代においても機械ではできないものです。
「どういうふうに作っているんだろう?」
「こういうふうにできてるんだぁ!」
という気付きが子どもたちには重要だと、参加した先生が教えてくださいました。

さすが先生…目の付け所が違います。

次回は山の体験、大谷崩れをレポートします。

2012年01月15日
歴史あるとろろ汁屋さんで食事です
こんにちは。
取材スタッフのケンです。
静岡市教育体験旅行モニターツアーはお昼ご飯の時間。
そしてお昼ご飯の会場はココ!

静岡市駿河区丸子の丁子屋(ちょうじや)さんです。
静岡市内でも有名なとろろ汁の名店ですが、それだけではありません。
まずは、その歴史がすごい!
なんと、安土桃山時代から450年も続くお店なのです!

歌川広重の浮世絵にも出てくるとろろ汁屋さんなのです!

店内には、かつて使用していた道具や資料も展示してあります。

若旦那の説明によると、
歌川広重の東海道五十三次の浮世絵53枚すべてを保存しており、
日替わりで1枚ずつ展示しているそうです。
テレビの某鑑定番組に出品したところ、5,000万円の値段がついたそうですよ。
子どもたちも興味を持って見学してくれると思います。
実は私はここに来るまでとろろ汁が苦手で、初めて丁子屋さんに入店したのですが、
いただいたとろろ汁はとてもおいしく感じました。
子どもたちの食わず嫌いも克服できるのでは?!
次回は駿府匠宿をレポートします。
取材スタッフのケンです。

静岡市教育体験旅行モニターツアーはお昼ご飯の時間。
そしてお昼ご飯の会場はココ!

静岡市駿河区丸子の丁子屋(ちょうじや)さんです。

静岡市内でも有名なとろろ汁の名店ですが、それだけではありません。
まずは、その歴史がすごい!
なんと、安土桃山時代から450年も続くお店なのです!

歌川広重の浮世絵にも出てくるとろろ汁屋さんなのです!

店内には、かつて使用していた道具や資料も展示してあります。


若旦那の説明によると、
歌川広重の東海道五十三次の浮世絵53枚すべてを保存しており、
日替わりで1枚ずつ展示しているそうです。

テレビの某鑑定番組に出品したところ、5,000万円の値段がついたそうですよ。
子どもたちも興味を持って見学してくれると思います。

実は私はここに来るまでとろろ汁が苦手で、初めて丁子屋さんに入店したのですが、
いただいたとろろ汁はとてもおいしく感じました。

子どもたちの食わず嫌いも克服できるのでは?!
次回は駿府匠宿をレポートします。

2012年01月14日
弥生時代の生活を体験!火おこし体験!
こんにちは。
取材スタッフのケンです。
静岡市登呂博物館見学のその3!
火おこし体験です。

博物館の外には、高床式倉庫や住居が忠実に復元されています。
その目の前で、火おこし体験をさせてもらいました。
火おこしは「まいぎり」と呼ばれる道具を使って行います。

まいぎりを上下に動かして、摩擦熱で火種を作ります。
結構手が疲れます…

煙が出てきました。もう一息です!

火種を綿に移して、息を吹きかけたら…上手に付きました^^
火をおこすためのコツを学芸員の方に尋ねてみましたが、
「力を入れすぎず、抜きすぎず、とにかくがんばること!」
と言っていました。
小学生でも5分くらい、うまい子なら1分もすれば火がおこせるそうです。
そのほかにも、赤米(あかまい)作り、石器作り、勾玉作りなどの体験が用意されています。
組み合わせによって、短時間でも長時間でも学習できる施設です
なかでも学芸員さんのオススメは、赤米作り。
登呂遺跡では、弥生時代の生活を再現することで、
古代の体験を身近に感じてもらおうと、弥生人が食べていた古代米である赤米を土器で炊爨してくれます。

火を扱う体験なので体験用の復元住居の中で作ってくれます。
中は案外広く、子どもたちなら20人くらい入れそうです。
「そんなに多くは作れないけど、みんなでちょっとづつ食べてもらって、
炊飯器で炊いたお米との味比べなんかをして、
現代と古代の食文化の違いを感じてもらえたらと思います。」
とのことでした。
子どもたちの喜ぶ顔が目に浮かんでくるようです。
3回に渡ってお送りした登呂博物館レポートはここまで。
次回も引き続き、歴史に関係のある施設に伺いますよ!
取材スタッフのケンです。

静岡市登呂博物館見学のその3!
火おこし体験です。


博物館の外には、高床式倉庫や住居が忠実に復元されています。
その目の前で、火おこし体験をさせてもらいました。

火おこしは「まいぎり」と呼ばれる道具を使って行います。

まいぎりを上下に動かして、摩擦熱で火種を作ります。
結構手が疲れます…

煙が出てきました。もう一息です!


火種を綿に移して、息を吹きかけたら…上手に付きました^^
火をおこすためのコツを学芸員の方に尋ねてみましたが、
「力を入れすぎず、抜きすぎず、とにかくがんばること!」
と言っていました。
小学生でも5分くらい、うまい子なら1分もすれば火がおこせるそうです。
そのほかにも、赤米(あかまい)作り、石器作り、勾玉作りなどの体験が用意されています。
組み合わせによって、短時間でも長時間でも学習できる施設です

なかでも学芸員さんのオススメは、赤米作り。
登呂遺跡では、弥生時代の生活を再現することで、
古代の体験を身近に感じてもらおうと、弥生人が食べていた古代米である赤米を土器で炊爨してくれます。

火を扱う体験なので体験用の復元住居の中で作ってくれます。
中は案外広く、子どもたちなら20人くらい入れそうです。
「そんなに多くは作れないけど、みんなでちょっとづつ食べてもらって、
炊飯器で炊いたお米との味比べなんかをして、
現代と古代の食文化の違いを感じてもらえたらと思います。」
とのことでした。

子どもたちの喜ぶ顔が目に浮かんでくるようです。

3回に渡ってお送りした登呂博物館レポートはここまで。
次回も引き続き、歴史に関係のある施設に伺いますよ!