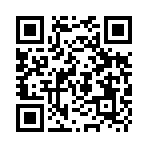2012年01月10日
三保・梅ヶ島教育体験旅行を終えて★
こんにちは!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!
横浜市立もえぎ野小学校の子どもたちは久能山東照宮を見学した後、
お昼ご飯を食べて、横浜へ帰って行きました。
子どもたちにとって長いようであっという間の2泊3日でした


今回の教育体験旅行は、様々な角度から静岡市を体験・学習するものでした。
三保での海洋体験や梅ヶ島での自然体験、歴史に食の体験
そしてその軸には、静岡市の山と海を繋いでいる安倍川があり、
全体の体験学習の流れにストーリー性を出し、静岡市でしか体験できないものにしています。
しずおかの恵み体感協議会の方々が「静岡市らしさ」に要点を置き、各プログラムを考えているのがよくわかりました。

また、体験プログラムの中でも、人との繋がりを大事に考えられていたと思います
海洋体験のインストラクターからは、安全管理を徹底した上で、
海洋スポーツの楽しさや海の恐さなどを学んでもらいたいという熱い想いが伝わってきました。
大谷崩の森林インストラクターからは、
子どもたちと近い目線で、自由に環境や歴史を学んでもらおうという姿勢が感じられました。
また、梅ヶ島では、地域のお母さん方が出向いてくれていっしょにヤマメを調理したり、
お父さん方が伝統の神楽を披露したりと、
子どもたちを温かくもてなそうとする気持ちが十分に表れていました
2泊3日で何が心に残っている?という質問に、
「梅ヶ島の人たちといっしょに踊った、キャンプファイヤー」と答える子どももいました。

子どもたちは普段なかなか関わることのない、海や山の体験をとても楽しく過ごし、
美しい風景を見たり、驚きの体験をしたりした時、素直に感動し喜んでいました
やはり、こういう感動は子どもの時にこそ味わってもらいたいものだと思います。

今の子どもたちは、人とコミュニケーションを図る機会が減少していると言われています。
横浜の子どもたちは、今回の2泊3日の教育体験旅行で、
自然体験や集団生活を経験し、知識だけでなく、人とふれあう喜びを学んだと思います!
是非、この体験を通して、大人になっても「静岡にまた行きたいなぁ」と思ってほしいものですね
これで梅ヶ島・三保教育体験旅行のレポートは終わります!
ではまた次回
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!

横浜市立もえぎ野小学校の子どもたちは久能山東照宮を見学した後、
お昼ご飯を食べて、横浜へ帰って行きました。
子どもたちにとって長いようであっという間の2泊3日でした


今回の教育体験旅行は、様々な角度から静岡市を体験・学習するものでした。
三保での海洋体験や梅ヶ島での自然体験、歴史に食の体験

そしてその軸には、静岡市の山と海を繋いでいる安倍川があり、
全体の体験学習の流れにストーリー性を出し、静岡市でしか体験できないものにしています。
しずおかの恵み体感協議会の方々が「静岡市らしさ」に要点を置き、各プログラムを考えているのがよくわかりました。
また、体験プログラムの中でも、人との繋がりを大事に考えられていたと思います

海洋体験のインストラクターからは、安全管理を徹底した上で、
海洋スポーツの楽しさや海の恐さなどを学んでもらいたいという熱い想いが伝わってきました。
大谷崩の森林インストラクターからは、
子どもたちと近い目線で、自由に環境や歴史を学んでもらおうという姿勢が感じられました。
また、梅ヶ島では、地域のお母さん方が出向いてくれていっしょにヤマメを調理したり、
お父さん方が伝統の神楽を披露したりと、
子どもたちを温かくもてなそうとする気持ちが十分に表れていました

2泊3日で何が心に残っている?という質問に、
「梅ヶ島の人たちといっしょに踊った、キャンプファイヤー」と答える子どももいました。
子どもたちは普段なかなか関わることのない、海や山の体験をとても楽しく過ごし、
美しい風景を見たり、驚きの体験をしたりした時、素直に感動し喜んでいました

やはり、こういう感動は子どもの時にこそ味わってもらいたいものだと思います。
今の子どもたちは、人とコミュニケーションを図る機会が減少していると言われています。
横浜の子どもたちは、今回の2泊3日の教育体験旅行で、
自然体験や集団生活を経験し、知識だけでなく、人とふれあう喜びを学んだと思います!

是非、この体験を通して、大人になっても「静岡にまた行きたいなぁ」と思ってほしいものですね

これで梅ヶ島・三保教育体験旅行のレポートは終わります!
ではまた次回

2012年01月09日
3日目久能山東照宮を見学
 こんにちは。
こんにちは。取材スタッフのケンです。

前回の有東木から南下して、久能山東照宮の見学です。
ここは、駿府城で過ごした、時の天下人・徳川家康が亡くなる直前に
「遺骸は、久能山に埋葬すること」
を遺命として託し、埋葬されたことで有名です。
日光の東照宮よりも前の時代に作られており、
2010年12月に本殿・石の間・拝殿が、静岡県内の建築物として初めて国宝に指定されました。

また、2006年に、50年に一度の漆の塗り替え工事が行われたため、現在は造営当初のような、
美しい社殿、諸建造を見学することができます。

今回は日本平山頂からロープウェイで向かいます。


実は、御前崎から久能山東照宮を線で結んだ延長線上には富士山、さらに群馬県の世良田東照宮(徳川氏祖先の地)があり、さらに延長すると、日光東照宮があるのです。
なので、久能山の東照宮でお参りをすると、世良田や日光の東照宮に手を合わせているのと同じことになるのだそうですよ。


子どもたちは、来年は日光の東照宮に行くそうです、
社殿の作りや規模など、久能山の東照宮と比べてみたりして、違いや、歴史、文化を感じてもらえたらなぁ…と思いました。

2012年01月08日
有東木、山葵(わさび)田見学
こんにちは。
取材スタッフのケンです。

梅ヶ島の方と別れを告げ、
梅ヶ島から有東木へ舞台を移し、山葵(わさび)田の見学を行いました。
ちなみに有東木は「うとうぎ」と読むのです。

ここ有東木は梅ヶ島の隣町、日本のわさび栽培発祥の地です。
有東木は古くからわさびの群生地となっていましたが、その苗を湧水地に植え替え栽培されたのが始まりです。
1607年、駿府城に入城した大御所徳川家康公に献上したところ、
その珍味を賞賛され、天下の逸品として村から門外不出の御法度品としました。
徳川家の御紋も『葵』ですから大事にされていたのではないか、と地元農家の方も話していました。
お茶と山葵の里と呼ばれ、
全国でもお茶畑と山葵田が同時に見られるのはここだけではないでしょうか。
同じ市内なのにここに来るまで全然知らなかったですorz

ここでは、ハイキングをしながら、
地元の山葵農家の方から山葵の歴史や栽培方法などを聞きました。
栽培者の生の声を聞き、食の学習に繋がります。
さらに、少し登ったところに白髭神社という小さな神社があり
樹齢約750年の杉の木があります。

すごく…大きいです…
食に歴史あり、土地に神あり、
有東木はそんなことも教えてくれるのかもしれませんね。
取材スタッフのケンです。


梅ヶ島の方と別れを告げ、
梅ヶ島から有東木へ舞台を移し、山葵(わさび)田の見学を行いました。
ちなみに有東木は「うとうぎ」と読むのです。


ここ有東木は梅ヶ島の隣町、日本のわさび栽培発祥の地です。
有東木は古くからわさびの群生地となっていましたが、その苗を湧水地に植え替え栽培されたのが始まりです。
1607年、駿府城に入城した大御所徳川家康公に献上したところ、
その珍味を賞賛され、天下の逸品として村から門外不出の御法度品としました。
徳川家の御紋も『葵』ですから大事にされていたのではないか、と地元農家の方も話していました。

お茶と山葵の里と呼ばれ、
全国でもお茶畑と山葵田が同時に見られるのはここだけではないでしょうか。

同じ市内なのにここに来るまで全然知らなかったですorz

ここでは、ハイキングをしながら、
地元の山葵農家の方から山葵の歴史や栽培方法などを聞きました。
栽培者の生の声を聞き、食の学習に繋がります。
さらに、少し登ったところに白髭神社という小さな神社があり
樹齢約750年の杉の木があります。

すごく…大きいです…

食に歴史あり、土地に神あり、
有東木はそんなことも教えてくれるのかもしれませんね。

2012年01月07日
梅ヶ島神楽とソーラン節
こんにちは。
取材スタッフのケンです。
今回の教育体験旅行、初めての試みだった梅ヶ島地区では、子どもたちをおもてなしするために、
梅ヶ島神楽をプレゼントして下さいました。

梅ヶ島に伝わるこの神楽ですが150年以上の歴史があり、
2月最初の牛の日、初午(はつうま)の日に行われるものです。
静岡市指定無形民俗文化財に指定されており、梅ヶ島の人々ができる精一杯のおもてなしをこの神楽で表現してくれました。

子どもたちも真剣な眼差しです。
神楽のお返しにと、子どもたちがソーラン節を披露してくれました。

伝統芸能への関心を高め、子どもたちと地域の方の文化交流に、
キャンプファイヤーがよい雰囲気を演出しています
そういえば、横浜の小学校なのに、なぜにソーラン節なのだろう
と思ったのですが……
実は、コレ、彼らが今年の運動会で発表するために、
何日もかけて練習してきた自慢の踊りらしいのです。
最後には地元の方と一緒になって踊りました。
文化交流と言ってしまえば簡単ですが、キャンプファイヤーに照らされて舞う子どもたちは、
なんとも幻想的で、素敵なひと時となりました。
取材スタッフのケンです。

今回の教育体験旅行、初めての試みだった梅ヶ島地区では、子どもたちをおもてなしするために、
梅ヶ島神楽をプレゼントして下さいました。

梅ヶ島に伝わるこの神楽ですが150年以上の歴史があり、
2月最初の牛の日、初午(はつうま)の日に行われるものです。
静岡市指定無形民俗文化財に指定されており、梅ヶ島の人々ができる精一杯のおもてなしをこの神楽で表現してくれました。


子どもたちも真剣な眼差しです。
神楽のお返しにと、子どもたちがソーラン節を披露してくれました。


伝統芸能への関心を高め、子どもたちと地域の方の文化交流に、
キャンプファイヤーがよい雰囲気を演出しています

そういえば、横浜の小学校なのに、なぜにソーラン節なのだろう

と思ったのですが……
実は、コレ、彼らが今年の運動会で発表するために、
何日もかけて練習してきた自慢の踊りらしいのです。
最後には地元の方と一緒になって踊りました。

文化交流と言ってしまえば簡単ですが、キャンプファイヤーに照らされて舞う子どもたちは、
なんとも幻想的で、素敵なひと時となりました。
2012年01月06日
夕食バーベキュー!
 おはようございます。
おはようございます。取材スタッフのケンです。

今回の記事は梅ヶ島体験学習2日目夜の部、
そう…バーベキューです!!

宿泊先の一つである金山温泉の施設では150人のバーベキューも可能です。
自分の手で採ったヤマメと、原木から採ってきたばかりのシイタケに味付けして食します。
お昼の体験と結び合わせて、食の学習にもつながります。

メインディッシュは魚魚の里(ととのさと)で釣り上げた、ヤマメの塩焼きです。
ヤマメは串に刺し、じっくり、しっかりと焼きます。
これで水分がとぶことで頭からまるかじりできるんです。


シイタケ農家さんで子どもたちが採ってきたシイタケです。
肉厚のシイタケはとっても食感が良く、普段自分が家で食べているものと同じとは思えないほどおいしかったです。


昼間の盛りだくさんの体験でお腹が減ったからか、
みなさん食欲旺盛でした。

協議会としても、食のプログラムにはこだわりがあり、
山でしか食べることのできない食材、しかも自分の手で採れたものをすぐに調理する食べ物を頭をひねって考えたそうです。
アレルギーのある子どもには特別メニューを用意したり、
生焼けの食材を食べないように、各鉄板には協議会のメンバーがしっかりと焼いてくれていました。

2012年01月05日
大谷崩散策と椎茸の収穫体験☆
こんにちは!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!
魚魚(とと)の里での自然体験後バスで大谷崩(おおやくずれ)へ移動。

大谷崩
大谷崩は日本三大崩れのひとつであり、本格的な崩壊は江戸時代にまでさかのぼるとされています。
また全国で唯一、水源から河口までを同一市内で完結している一級河川「安倍川」の源頭部分です。

三保の東海大学海洋科学博物館で説明を受けたように、
三保で見られたハチマキ石がここでも見つけられました

しかし、三保のものよりも…でかい!角張っている!
それは梅ヶ島のハチマキ石が安倍川を伝っている間に角が削られ小さくなり、
やがて三保に流れ着いたという証拠になるのです。
なるほど、今回の体験旅行の舞台が一本の線ならぬ川で繋がるわけですね!
これが今回の教育体験旅行のテーマで、ただ海と山の体験を別々で行うのではなく、
ストーリーやオリジナリティを持たせることで、静岡市でしかできない教育体験旅行となるのです。
協議会の方は、そういったことを重視し体験旅行の行程を組んだそうです。

子どもたちはインストラクターといっしょに大谷崩を散策
みんなでお気に入りの石を収集ターイム!
「この石は何でできてるの?この石のこの色の部分はなに?」
とインストラクターは質問攻めにあっていました
「この石の白い模様の部分は、石英と言って水晶と同じ組成の脈なんだよ」
とインストラクターが丁寧に説明、
「水晶が含まれている石もあるよ」と言うと子どもたちは必死で探していました笑
また保管されているミミズの化石を見ることができるなど、石などの説明から地質、地形についても学びました。

椎茸の収穫体験
椎茸栽培農家のもとで椎茸の収穫をさせていただきました。
子どもたちは椎茸が木に生えているのを初めて見てびっくり! (わたしもです…)
(わたしもです…)
農家さんが椎茸の栽培方法を教えてくれます。

採れたての椎茸はバーベキューで食べます
バスで魚魚の里に戻り、
次回はいざバーベキューです♪
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!

魚魚(とと)の里での自然体験後バスで大谷崩(おおやくずれ)へ移動。
大谷崩
大谷崩は日本三大崩れのひとつであり、本格的な崩壊は江戸時代にまでさかのぼるとされています。
また全国で唯一、水源から河口までを同一市内で完結している一級河川「安倍川」の源頭部分です。
三保の東海大学海洋科学博物館で説明を受けたように、
三保で見られたハチマキ石がここでも見つけられました


しかし、三保のものよりも…でかい!角張っている!
それは梅ヶ島のハチマキ石が安倍川を伝っている間に角が削られ小さくなり、
やがて三保に流れ着いたという証拠になるのです。
なるほど、今回の体験旅行の舞台が一本の線ならぬ川で繋がるわけですね!

これが今回の教育体験旅行のテーマで、ただ海と山の体験を別々で行うのではなく、
ストーリーやオリジナリティを持たせることで、静岡市でしかできない教育体験旅行となるのです。
協議会の方は、そういったことを重視し体験旅行の行程を組んだそうです。
子どもたちはインストラクターといっしょに大谷崩を散策

みんなでお気に入りの石を収集ターイム!

「この石は何でできてるの?この石のこの色の部分はなに?」
とインストラクターは質問攻めにあっていました

「この石の白い模様の部分は、石英と言って水晶と同じ組成の脈なんだよ」
とインストラクターが丁寧に説明、
「水晶が含まれている石もあるよ」と言うと子どもたちは必死で探していました笑

また保管されているミミズの化石を見ることができるなど、石などの説明から地質、地形についても学びました。
椎茸の収穫体験
椎茸栽培農家のもとで椎茸の収穫をさせていただきました。
子どもたちは椎茸が木に生えているのを初めて見てびっくり!
 (わたしもです…)
(わたしもです…)農家さんが椎茸の栽培方法を教えてくれます。
採れたての椎茸はバーベキューで食べます

バスで魚魚の里に戻り、
次回はいざバーベキューです♪

2012年01月04日
ヤマメ釣り体験★
こんにちは!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです

■魚魚(とと)の里での自然体験の続き■

ヤマメ釣り
魚魚の里には3つの池があり、そこに放たれているヤマメを釣ります。
最初はなかなかヤマメを釣ることができませんでしたが、
少しするとコツをつかんだのか、みんなどんどん釣り上げていました♪
しかし、釣れてもヤマメに触ることができずあたふたする子も

きっとこの時、初めて生きた魚に触った子もいるのではないでしょうか。

釣り上げたヤマメは夜のバーベキューで食べるため
その場で地元のおばちゃんたちに教わりながら調理します。
ヤマメ釣りは、自分たちで釣った魚を調理し焼いて食べるという食の体験に繋がっていたのです
子どもたちは、ヤマメの体を切って内臓を取り出し串で刺す作業に
表情が曇っていましたが、優しいおばちゃんたちの笑顔に見守られながら作業を行っていました。

「やっぱり元気が1番。静岡の子も横浜の子もいっしょだね」
と笑顔で言ったおばちゃんの言葉が印象に残っています
教育体験旅行は、こういった地域の人との「心」の交流に意味があると思います。
次回は大谷崩の散策と椎茸の収穫体験です!ではっ
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです


■魚魚(とと)の里での自然体験の続き■
ヤマメ釣り
魚魚の里には3つの池があり、そこに放たれているヤマメを釣ります。
最初はなかなかヤマメを釣ることができませんでしたが、
少しするとコツをつかんだのか、みんなどんどん釣り上げていました♪
しかし、釣れてもヤマメに触ることができずあたふたする子も


きっとこの時、初めて生きた魚に触った子もいるのではないでしょうか。
釣り上げたヤマメは夜のバーベキューで食べるため
その場で地元のおばちゃんたちに教わりながら調理します。
ヤマメ釣りは、自分たちで釣った魚を調理し焼いて食べるという食の体験に繋がっていたのです

子どもたちは、ヤマメの体を切って内臓を取り出し串で刺す作業に
表情が曇っていましたが、優しいおばちゃんたちの笑顔に見守られながら作業を行っていました。
「やっぱり元気が1番。静岡の子も横浜の子もいっしょだね」
と笑顔で言ったおばちゃんの言葉が印象に残っています

教育体験旅行は、こういった地域の人との「心」の交流に意味があると思います。
次回は大谷崩の散策と椎茸の収穫体験です!ではっ

2012年01月03日
箸作り&ネイチャーゲーム☆
こんにちは!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!

~魚魚の里で自然体験の続き~

箸作り
木を削って滑らかになるまで磨き、箸を作るものづくり体験。
みんな真剣にインストラクターの方に教わりながら作っていました!
自分で作ったマイ箸で食べるご飯は一段とおいしく感じられるのではないでしょうか?!

ネイチャーゲーム
インストラクターと、「だるまさんが転んだ」などのゲームをしました

かなりゲームがエキサイティングだったので、
昨日の海洋体験で子どもたちが疲れていないか心配しましたが…心配ご無用!
開放感あふれる自然の中で、思いっきり体を動かし、笑顔で楽しんでいました
ゲームの内容が、友達との協調性やコミュニケーションを大事にしたもので
ただ遊ぶだけでなく、しっかり学習効果にもこだわって作られているなぁと感心しました。
次回はヤマメ釣り体験です!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!


~魚魚の里で自然体験の続き~
箸作り
木を削って滑らかになるまで磨き、箸を作るものづくり体験。
みんな真剣にインストラクターの方に教わりながら作っていました!

自分で作ったマイ箸で食べるご飯は一段とおいしく感じられるのではないでしょうか?!

ネイチャーゲーム
インストラクターと、「だるまさんが転んだ」などのゲームをしました


かなりゲームがエキサイティングだったので、
昨日の海洋体験で子どもたちが疲れていないか心配しましたが…心配ご無用!

開放感あふれる自然の中で、思いっきり体を動かし、笑顔で楽しんでいました

ゲームの内容が、友達との協調性やコミュニケーションを大事にしたもので
ただ遊ぶだけでなく、しっかり学習効果にもこだわって作られているなぁと感心しました。
次回はヤマメ釣り体験です!

2012年01月02日
香炉作り☆
こんにちは!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんですー
三保・梅ヶ島の教育体験旅行2日目は、梅ヶ島の
魚魚(とと)の里の自然体験から始まります!
朝、子どもたちは各旅館からバスで魚魚の里に集合です。

魚魚の里はさまざまな自然体験ができる施設です。
各プログラムをクラスごとに順番に体験していきました。

香炉作り
木を組み立てて作ります。中にキャンドルを入れ火をつけることで
敷いたアルミホイルの上のお茶の葉や花からいい香りがでる仕組みになっています
お洒落なものづくり体験です♪
加熱することで、花やお茶の葉からこんなにいい香りが生まれるなんて
子どもたちは知らなかったと思います。
みんないろいろな花を乗せて香りや見た目を楽しんでいました
次回は箸作りとネイチャーゲームです!では!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんですー

三保・梅ヶ島の教育体験旅行2日目は、梅ヶ島の
魚魚(とと)の里の自然体験から始まります!
朝、子どもたちは各旅館からバスで魚魚の里に集合です。
魚魚の里はさまざまな自然体験ができる施設です。
各プログラムをクラスごとに順番に体験していきました。
香炉作り
木を組み立てて作ります。中にキャンドルを入れ火をつけることで
敷いたアルミホイルの上のお茶の葉や花からいい香りがでる仕組みになっています

お洒落なものづくり体験です♪
加熱することで、花やお茶の葉からこんなにいい香りが生まれるなんて
子どもたちは知らなかったと思います。
みんないろいろな花を乗せて香りや見た目を楽しんでいました

次回は箸作りとネイチャーゲームです!では!

2012年01月01日
梅ヶ島へ!★
こんにちは!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!
三保での海洋体験が終わり、バスで梅ヶ島に移動
舞台が海から山に移ります!

梅ヶ島の人たちから温かい歓迎を受けながら開校式を行いました。
「よろしくお願いします!」と梅ヶ島の人たちにご挨拶。
「歓迎 横浜市立もえぎ野小学校様」と書かれた横断幕が用意されていて、
先生方は「こんなことは初めてです」と驚いていました

梅ヶ島の方々も横浜の子どもたちが来ることを楽しみにしていたんですね

その後、クラスで各旅館に分かれ、梅ヶ島で採れた山の食材を用いた夕食を食べました
おいしそう 子どもたちも大喜びです♪
子どもたちも大喜びです♪
食べながら、旅館の方が子どもたちに
「これは3日目に行く有東木(うとうぎ)で採れた山葵(わさび)で、綺麗で美味しい水で育てているんだよー」
など食材について説明していました。
有東木の人たちは、子供の頃から山葵を見てきており、自分ですりおろして食べることが一般的だそうです。
ただ食べるだけじゃなく、地元で採れた食材を地元の方に説明されながら食べると、
さらにおいしく感じられますね
この梅ヶ島でしか味わうことのできない食の体験です。
そして2日目の梅ヶ島の体験に向けて就寝しました…
次回は2日目の体験から始まります!
教育体験旅行取材チームのよーちゃんです!

三保での海洋体験が終わり、バスで梅ヶ島に移動

舞台が海から山に移ります!
梅ヶ島の人たちから温かい歓迎を受けながら開校式を行いました。
「よろしくお願いします!」と梅ヶ島の人たちにご挨拶。
「歓迎 横浜市立もえぎ野小学校様」と書かれた横断幕が用意されていて、
先生方は「こんなことは初めてです」と驚いていました


梅ヶ島の方々も横浜の子どもたちが来ることを楽しみにしていたんですね

その後、クラスで各旅館に分かれ、梅ヶ島で採れた山の食材を用いた夕食を食べました

おいしそう
 子どもたちも大喜びです♪
子どもたちも大喜びです♪食べながら、旅館の方が子どもたちに
「これは3日目に行く有東木(うとうぎ)で採れた山葵(わさび)で、綺麗で美味しい水で育てているんだよー」
など食材について説明していました。
有東木の人たちは、子供の頃から山葵を見てきており、自分ですりおろして食べることが一般的だそうです。
ただ食べるだけじゃなく、地元で採れた食材を地元の方に説明されながら食べると、
さらにおいしく感じられますね

この梅ヶ島でしか味わうことのできない食の体験です。
そして2日目の梅ヶ島の体験に向けて就寝しました…

次回は2日目の体験から始まります!